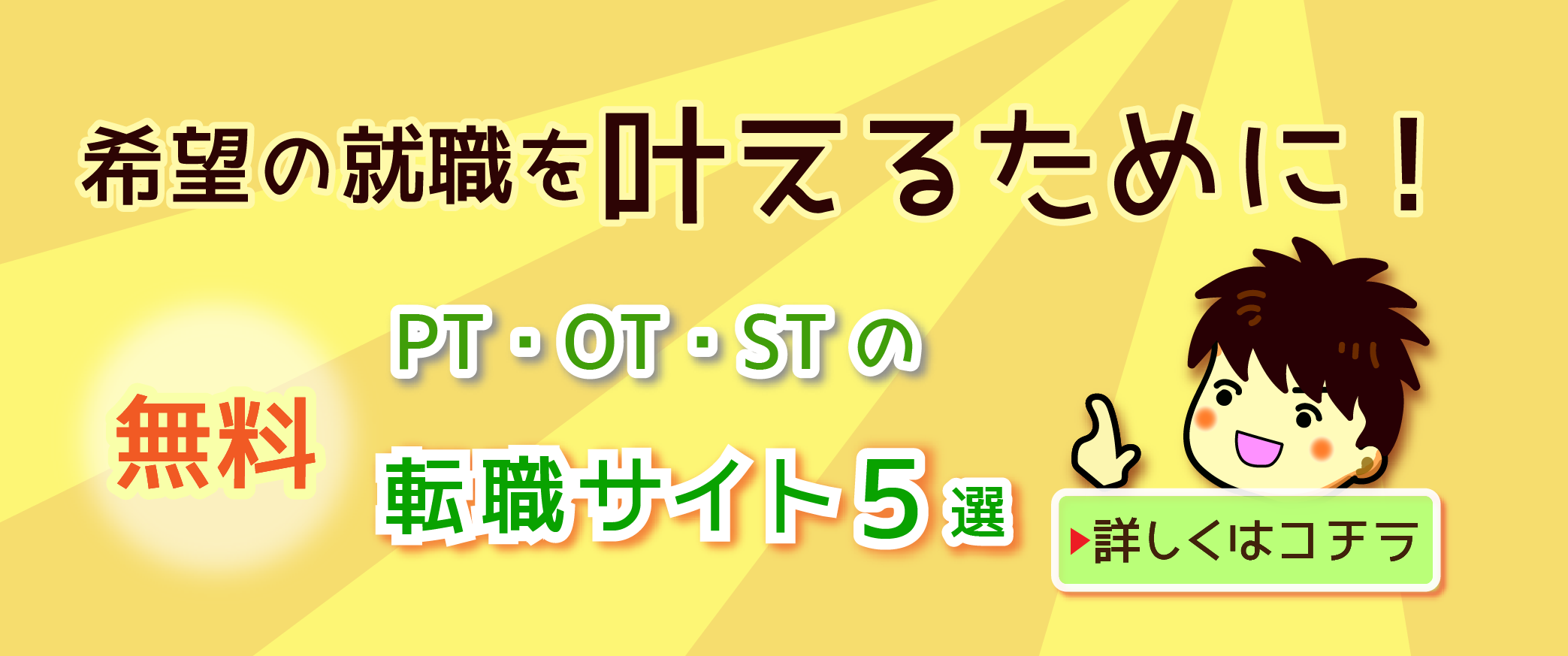高次脳機能障害の一つのに失行症というものがあります。
医療に携わる人、特にリハビリに従事する人で失行(症)を知らない人はまずいないでしょう。
失行とは、その名の通りの「行為を失う」ということです。
つまり、できる身体機能を有しているのに、何らかの行為ができない症状がみられることをいいます。
失行は単独で症状がみられることは稀で、認知症や他の高次脳機能障害、身体機能の問題などが複雑に絡み合ってみられることが多いです。
それ故に、できていない現象だけをみていると、短絡的に「これは失行だ!」と決めつけてしまうことにもなります。
理学療法士や作業療法士は失行については、ある程度理解はしていると思います。
「失行は意識すると動作ができず、無意識なら動作ができる。」
くらいの理解で足踏みしている療法士の人は、是非この記事を読んで理解を深めてほしいと思います。
失行とは何か?
その原因やメカニズムを理解していれば、何を評価すれば良いのか、どんなリハビリが良いのかがわかってきます。
スポンサーリンク
目次
失行(症)の定義
失行とは、
「麻痺や運動失調、筋緊張異常などその他の身体機能の障害はみられないにも関わらず、運動の行為ができない状態」
をいいます。
失行の原因とメカニズム
失行の原因やメカニズムをある程度知っていると、評価やリハビリで何をすればよいかがわかってきますので説明しておきます。
失行の原因
失行は、左優位半球(特に頭頂葉)の障害でみられることが多いですが、前頭葉の障害でも起こり得ます。
詳しい病巣については、後述しています。
失行のメカニズム
人が動く場合、そのほとんどは無意識です。
なぜ健常人は無意識に運動が行えるかというと、元々運動プログラムが脳内に組み込まれているからです。
それは過去の経験、もっというと過去に得た感覚から習得した技能です。
また、道具を使う場合も同様のことがいえます。
道具という感覚情報を感覚受容器がキャッチして、脳内で意味付けを行い(認知すること)、その感覚情報を元に解釈して、適切な運動が行われます。
人が運動を行う場合には、感覚情報を脳内で統合して運動を実現させています。
つまり、インプットーアウトプットの流れが必要になります。
失行は、このインプットーアウトプットのどちらか、または両方に支障を来しているということです。
そのため、運動連合野や頭頂連合野など、脳内で情報を集約・統合するような場所に障害があると失行症状がみられやすくなります。
失行の種類(肢節運動失行、観念運動失行、観念失行、その他)
失行の代表的なものとしては、Liepmannが最初に分類した以下の3つが有名です。
①肢節運動失行
②観念運動失行
③観念失行
④その他(構成失行・着衣失行)
①肢節運動失行
肢節運動失行は、熟練した動作ができなくなることをいいます。
さらに以下の3つに分類されます。
歩行失行
歩く際に足が上手く前に出ない
手指失行
手指を順序良く屈伸できない
顔面失行
口を開く、舌を出す、口笛を吹くなどができない
観念運動失行
例えば、手でグー・チョキ・パーをする、足で空中に円を描くなどの動きをする場合、
自発的にはできるのに、他者から指示されるとできなくなるのが特徴です。
また、動作の実行の中で時間的・空間的な異常もみられます。
例えば、バイバイと手を振る際に、ゆっくりと動かしたり、ぎこちない動きになることもあります。
道具の使用に際しても、道具の正しい持ち方がわからなくなります。
例えば、ハサミを持つのに上下逆に持ってしまいます。
観念失行
観念失行とは、複数物品の系列的に意味づけができなくなることをいいます。
例えば、
お茶を入れる際に、急須へお茶の葉を入れることができない、それを湯飲みに入れるにはどうすればいいのかわからないということが起こります。
観念失行は、複数物品の使用方法の意味付けの障害であるのに対して、観念運動失行は単一物品の使用方法の障害とされる場合もあります。
観念失行と観念運動失行は別に存在するわけではなく、合併している場合も多いです。
④構成失行・着衣失行
構成失行
船や家の絵を描いてもらうと上手く描けない、マッチ棒で三角や四角を作れないなどの構成機能の障害がみられます。
着衣失行
衣服の着脱にのみ支障を来すものをいいます。
実際には、構成失行や半側空間無視、身体失認などを合併している場合が多いです。
失行の病巣
失行は、インプットーアウトプットの流れのどこかに障害があります。
失行はほとんどが優位半球の障害で起こり、例えば右利きの人は左の脳が優位半球になります。
肢節運動失行の病巣
優位半球の前頭葉上部(中心前回、補足運動野や運動前野)の障害で起こります。
これらの場所は、過去の経験から運動を出力する場所です。
これらに障害が起きると元々プログラム化されていた運動がなくなってしまうため、運動ができなくなってしまいます。
肢節運動失行は、インプットーアウトプットのアウトプットの障害であるといえます。
観念運動失行、観念失行の病巣
観念運動失行や観念失行は、インプットの障害によりその後アウトプットができなくなっています。
病巣としては、優位半球の頭頂葉下部(上頭頂小葉、角回、縁上回)に障害がみられます。
より広範囲の障害があれば、観念失行がみられやすくなります。
構成失行、着衣失行の病巣
これらは主に頭頂葉ー後頭葉の障害で起こり、優位・劣位半球のどちらの障害でも起こり得ます。
スポンサーリンク
失行の検査・評価
失行の評価は、スクリーニングと客観的評価の2つが用いられています。
肢節運動失行の検査
ポケットに手を入れてもらう
机の上の硬化をつかむ
歩行する
などの動作が上手くできるかを観察します。
観念運動失行、観念失行の検査
①模倣
②道具の使用
③道具を使った一連の動作
の3つをみます。
①模倣
起立や歩行(肢節運動失行)、バイバイ(観念運動失行)や口笛(顔面失行)など簡単な動作を行ってもらいます。
②道具の使用
ネジを回すなど、実際に道具を使用してもらったり、身振りだけで行えるかも観察します。
③道具を使った一連の動作
急須とお茶の葉、湯飲みを使ってお茶をいれられるかなどを観察します。
客観的評価
客観的評価としては、
●ウェスタン統合失語症検査(WAB)
●標準高次動作検査(SPTA)
これらの中に失行を評価する項目があります。
失行のリハビリ治療
失行に対するリハビリには、①機能改善型治療、②能力補填型治療、③環境調整型治療、④行動変容型治療、⑤能力代償型治療の5つがあります。
①機能改善型治療
低下している機能を反復して訓練します。
失行は、感覚ー運動の統合が困難で生じている症状のため、実際場面で反復して訓練するのは有効な手段です。
失行と一言に言っても、症状の重症度は様々です。
まずは、できる動作が何かを評価した上で、段階的に進めていきます。
具体的には、歩行中足が上がっていないのであれば、
視覚的手がかり(台に足を置くなど) → 手がかりなし → 実際の歩行へと展開していきます。
運動学習理論を知っていればアプローチの方法はいくつか考えられると思いますので、こちらも参考にしてください。
②能力補填型治療
特別な道具を使用して、使いやすいように工夫することをいいます。
③環境調整型治療
写真付きの手順を書いた説明書で確認したり、服の前後に目印をつけるなどの動作手順を補います。
④行動変容型治療
動作や行為を分解して、最後にそれらを一連の流れとして習得していきます。
例えば、
急須にお茶の葉を入れる
お湯を急須に入れる
湯飲みにお茶を入れる
の3つの動作を分解して習得して後にそれらを繋げていきます。
⑤能力代償型治療
失行以外の機能で代償することをいいます。
例えば、
認知機能や言語能力が保たれているのであれば、動作や行為を口に出しながら実行してもらいます。
失行と失認の違いについて
失行は、感覚ー運動の統合ができないことで動作に支障を来しています。
一方失認とは、感覚を認知できないことをいいます。つまり、本人にとっては感覚情報そのものがないのと同じことになっています。
失認の代表的なものでは左の半側空間無視がありますが、本人にとって左側は存在しないのと一緒です。
健常人には理解しにくいのですが、僕たちが上の空で歩いていたら左から来た人に全く気付かなかったのと同じような状態になっているということです。
参考記事)
まとめ
失行について比較的解釈しやすいように記載しました。
失行とは、インプット‐アウトプットを統合することができない症状であると理解しておくと良いです。
合わせて読んでおきたい記事