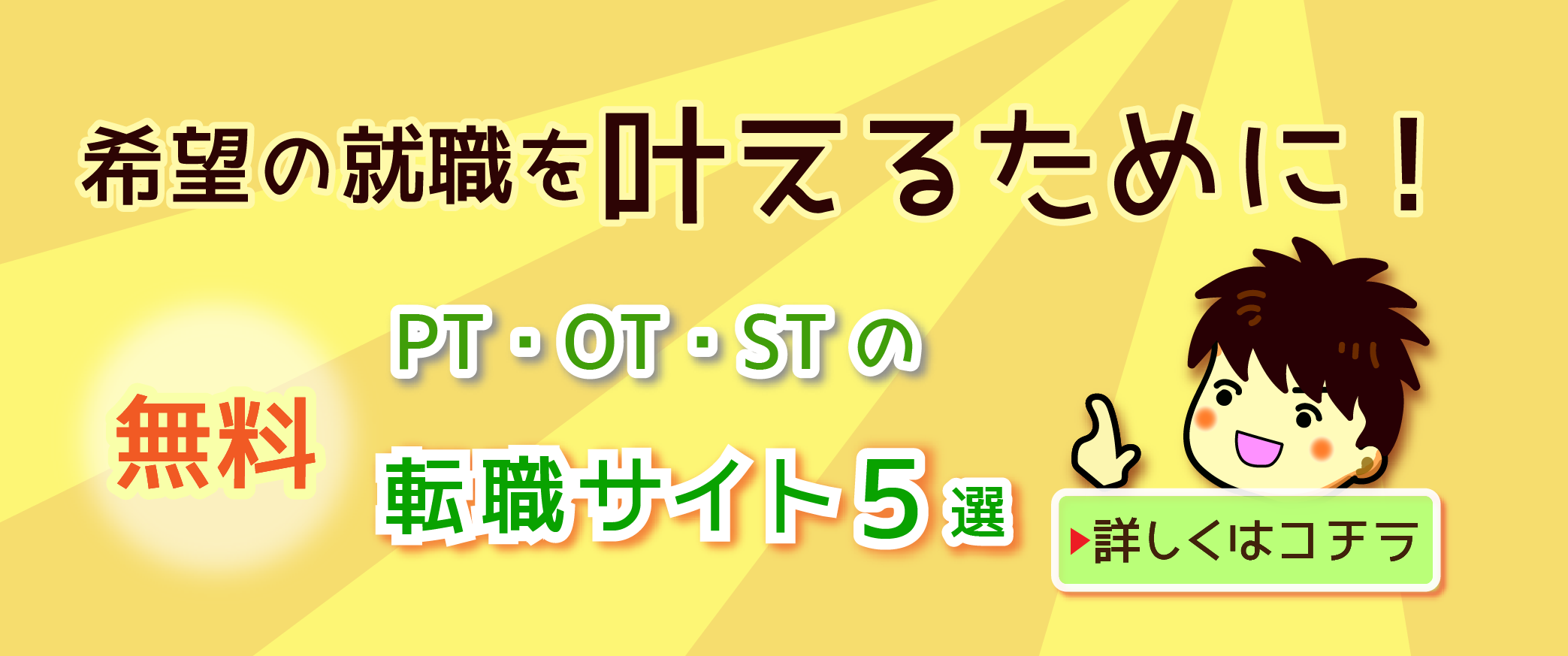「手や腕のしびれ、肩こりが続く…これって何?」
そんな不安を感じて調べている方へ。
「胸郭出口症候群」という言葉を初めて耳にする方も多いかもしれません。
この記事では、胸郭出口症候群の原因・リハビリ方法・治るまでの経過について、専門的な視点からわかりやすく解説します。
スポンサーリンク
目次
胸郭出口症候群とは?どんな病気?
胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)とは、首から腕にかけて伸びる神経や血管が、肩や鎖骨付近で圧迫されることによって起こる症状の総称です。
主な症状は以下の通りです。
- 手や腕のしびれ・だるさ
- 肩や首の痛み
- 握力の低下
- 動かすと悪化する(特に上に腕を上げたとき)
胸郭出口症候群の原因とは?
胸郭出口症候群の原因は、大きく3つのタイプに分かれます:
- 斜角筋症候群:首の前側にある筋肉(斜角筋)が硬くなり、神経を圧迫するタイプ
- 肋鎖症候群:鎖骨と第一肋骨の間で血管や神経が圧迫されるタイプ
- 過外転症候群:腕を上げた時に、小胸筋によって神経や血管が圧迫されるタイプ
1.斜角筋症候群
■ 圧迫を受ける神経
腕神経叢(わんしんけいそう)
- 首(頸椎)から出て、腕・手へと向かう神経の束。
- C5~T1の神経根から構成されており、運動や感覚を司ります。
- 斜角筋(特に前斜角筋と中斜角筋の間)を通過するため、ここで圧迫されることがあります。
鎖骨下動脈(さこつかどうみゃく)
神経ではありませんが、同じ部位で圧迫されることがあり、血流障害によって冷感やしびれが悪化します。
■ 関与する筋肉
前斜角筋(ぜんしゃかくきん)
- 頸椎(C3〜C6)から第1肋骨に付着。
- 神経と血管の「前側の壁」となる。
中斜角筋(ちゅうしゃかくきん)
- 頸椎(C2〜C7)から第1肋骨に付着。
- 神経と血管の「後ろ側の壁」となる。
この**前斜角筋と中斜角筋の間の隙間(斜角筋隙)**を神経と動脈が通過しており、これが狭くなることで圧迫が起こるのが、斜角筋症候群の本質です。
なぜ圧迫されるのか?
- 姿勢不良(猫背・ストレートネック)
- 首や肩の筋緊張(ストレスやデスクワーク)
- スポーツ・筋トレによる筋肥大
- 重たい荷物の持ち運び習慣
これらが原因で斜角筋が硬く・太くなると、腕神経叢が圧迫されやすくなります。
スポンサーリンク
2.肋鎖症候群
鎖骨と第一肋骨の間(肋鎖間隙)で腕神経叢や鎖骨下動脈・静脈が圧迫されて起こる症状です。
以下に「なぜなるのか?」という原因をわかりやすくまとめます。
■ 肋鎖症候群の主な原因
1. 不良姿勢(猫背・巻き肩)
猫背になると鎖骨が下がり、肋骨との隙間が狭くなるため、神経や血管が圧迫されやすくなります。
2. 筋肉の過緊張・筋肥大
特に小胸筋や僧帽筋の緊張によって、肩甲骨が下制・前傾し、鎖骨の位置が変わることで圧迫が起こります。
3. 外傷や手術の後遺症
鎖骨骨折や肩の外傷後、骨の変形や癒着などで構造的な狭窄が生じることがあります。
4. リュックや重い荷物の習慣
肩にかかる荷重が慢性的に加わると、鎖骨が下がり、肋鎖間隙が狭くなるリスクが高まります。
5. 先天的な骨格の異常
頸肋(けいろく)という余分な肋骨がある人や、鎖骨の形状異常がある人は、圧迫されやすくなります。
■ 肋鎖症候群になりやすい人の特徴
- 長時間のPC・スマホ使用者
- 筋トレや重量物の運搬を行う人
- なで肩や猫背の人
- 鎖骨周辺に外傷歴がある人
■ なぜ神経や血管が問題になるのか?
肋鎖間隙には以下の重要な構造が通っています。
- 腕神経叢(運動・感覚の神経)
- 鎖骨下動脈(血液を腕に送る)
- 鎖骨下静脈(血液を心臓へ戻す)
これらが狭い空間で押しつぶされると、しびれ・冷感・脱力感・腕のだるさなどの症状が出ます。
3,過外転症候群
腕を外に大きく上げたり(外転)、後ろに引いたときに、小胸筋によって神経や血管が圧迫されることで生じる症候群です。
胸郭出口症候群(TOS)の一タイプに分類されます。
スポンサーリンク
■ なぜ起こるのか?(原因)
● 小胸筋による圧迫
- 小胸筋(しょうきょうきん)は、第3〜5肋骨から肩甲骨の烏口突起につく筋肉。
- 腕を外転(バンザイのような動き)すると、小胸筋が神経や血管を押しつぶす動きになる。
■ 過外転症候群はどこで圧迫されるか
小胸筋の下で、神経・血管が肩甲骨と胸郭の間で圧迫されるのがポイントです。
● 神経や血管の通り道
- 小胸筋の下を、腕神経叢・鎖骨下動脈・鎖骨下静脈が通っている。
- 外転によりこの部位が狭くなると、圧迫が強くなり症状が出る。
■ どんな人がなりやすい?
|
リスク要因 |
内容 |
|
長時間の猫背姿勢 |
小胸筋が常に短縮状態になる |
|
デスクワーク |
肩が内巻きになりやすい |
|
重いものを肩にかける習慣 |
小胸筋に負担がかかる |
|
バンザイ姿勢を多く取る職業 |
理容師・電気工事・棚の上げ下ろしなど |
■ 症状
- 腕を挙げたときに出る
- しびれ・脱力感・だるさ
- 冷感や色の変化(血流障害)
- 特に「寝ている間に腕がしびれる」などの症状が出やすい
- 小胸筋部(胸の前方)を押すと痛みを感じることも
■ 治療・リハビリのポイント
- 小胸筋のストレッチ
- 壁を使った前腕の外旋ストレッチなど
- 姿勢改善
- 胸を開いて肩を正しい位置に戻す
- 手技療法や理学療法
- 小胸筋のリリースや可動域の改善
- 重い荷物・肩かけバッグを避ける
スポンサーリンク
胸郭出口症候群のリハビリ方法【理学療法士が解説】
胸郭出口症候群(TOS)のリハビリは、原因に応じた姿勢改善・筋緊張の緩和・可動域の確保を目的に進めます。
ここでは、理学療法士や医療従事者が取り入れる基本的なリハビリ方法をわかりやすく解説します。
基本方針:3つのポイント
- 神経や血管の通り道を「広げる」
- 原因筋(斜角筋・小胸筋など)を「ゆるめる」
- 不良姿勢を「整える」
リハビリ方法(一般的な運動療法)
壁立ちストレッチ(姿勢矯正)
壁立ちストレッチは、猫背や巻き肩、胸郭出口症候群の改善に効果的な「姿勢矯正ストレッチ」の一種です。
壁を使って正しい姿勢を身体に覚えさせることで、肩や首周りの緊張を緩和し、神経や血管の圧迫を減らす目的があります。
壁立ちストレッチのやり方
【手順】
- 壁に背を向けて立つ
かかと・お尻・背中・後頭部を壁につけて立ちます。膝は軽く伸ばす程度でOK。 - 肩甲骨を寄せる意識を持つ
肩が前に出ないように意識しながら、背中で壁を押すようにします。 - 腕を“バンザイ”の姿勢に
両肘を90度に曲げ、手の甲と肘が壁についた状態で「W」の形を作ります(これが難しい方は無理せずできる範囲でOK)。 - 腕を上にスライドさせる
「W」→「Y」の形になるように、肘と手の甲を壁につけたままゆっくり上下にスライドさせます。 - 10回程度繰り返す
壁立ちストレッチのポイント
- 腰が反らないように、お腹に軽く力を入れて行う
- 肩がすくまないようにリラックスする
- 痛みやしびれが出たらすぐに中止する
期待できる効果
- 巻き肩や猫背の改善
- 肩甲骨まわりの柔軟性アップ
- 胸郭出口症候群に関連する神経圧迫の軽減
- 呼吸がしやすくなる
肋骨・胸郭ストレッチ(呼吸と連動)
方法
- 椅子に座って片腕を頭上に上げ、逆方向に体を倒す
- 胸を開きながら深呼吸
- 20秒×3回ずつ左右
肋骨と鎖骨のスペース(肋鎖間隙)を広げます。
小胸筋ストレッチ
壁やドア枠を使う
- 肘を90度に曲げ、腕を壁にあてて胸を開く
- 手の高さを調整して、胸の前が伸びるのを意識
- 20秒×2~3回
過外転症候群の予防・改善に効果的
斜角筋リリース(筋膜リリース的手技)
自分で行う場合
- 鎖骨のすぐ上(首の横)を軽くつまむように圧迫
- リズムよく優しくマッサージ(1~2分)
斜角筋症候群に有効。※強く押しすぎないこと
スポンサーリンク
肩甲骨モビリティ運動(運動連鎖の回復)
肩甲骨回し・肩甲骨引き寄せ運動:
- 背中で肩甲骨を寄せるように5秒キープ
- 10回×2セット
肩甲帯全体の動き改善と安定性向上
注意点(病型別の配慮)
|
病型 |
注意点・対処法 |
|
斜角筋症候群 |
首のストレッチや圧迫に注意。急な回旋運動はNG。 |
|
肋鎖症候群 |
猫背姿勢・肩下がり姿勢に注意。胸を開く動き中心。 |
|
過外転症候群 |
小胸筋ストレッチを重点的に。バンザイ姿勢の頻用は避ける。 |
日常生活の動作指導
- 鞄はリュックに変える
- 肘を支点にした作業は短時間にする
- 長時間のスマホ・PC作業を避け、休憩を挟む
※痛みが強い場合は、無理にストレッチをせず、まずは整形外科や理学療法士に相談することが大切です。
補助的におすすめ
- 姿勢矯正用インナーやストレッチポール
- 適度な有酸素運動(血流改善)
- 鍼灸や温熱療法との併用
胸郭出口症候群は治る?リハビリの経過と回復期間
多くの方が気になるのが「治るのか」「どのくらいで良くなるのか」という点です。
一般的な回復までの流れ(目安)
- 初期(0〜2週間):痛みやしびれが強く、安静と軽いストレッチ中心
- 中期(2週間〜2ヶ月):姿勢矯正・筋肉の柔軟性改善・軽い運動療法を継続
- 後期(2ヶ月以降):負荷の高い運動も取り入れ、再発防止のトレーニングへ
軽症なら数週間〜1ヶ月程度で改善するケースもありますが、重度の場合は3ヶ月以上かかることも。
早期にリハビリを始めることが、回復を早めるポイントです。
スポンサーリンク
まとめ
胸郭出口症候群は正しく対処すれば改善できます
胸郭出口症候群は、放置すると日常生活に支障をきたすこともある症状です。
しかし、原因を知り、適切なリハビリを行うことで改善が期待できます。
不安な場合は、整形外科や理学療法士などの専門家に早めに相談しましょう。