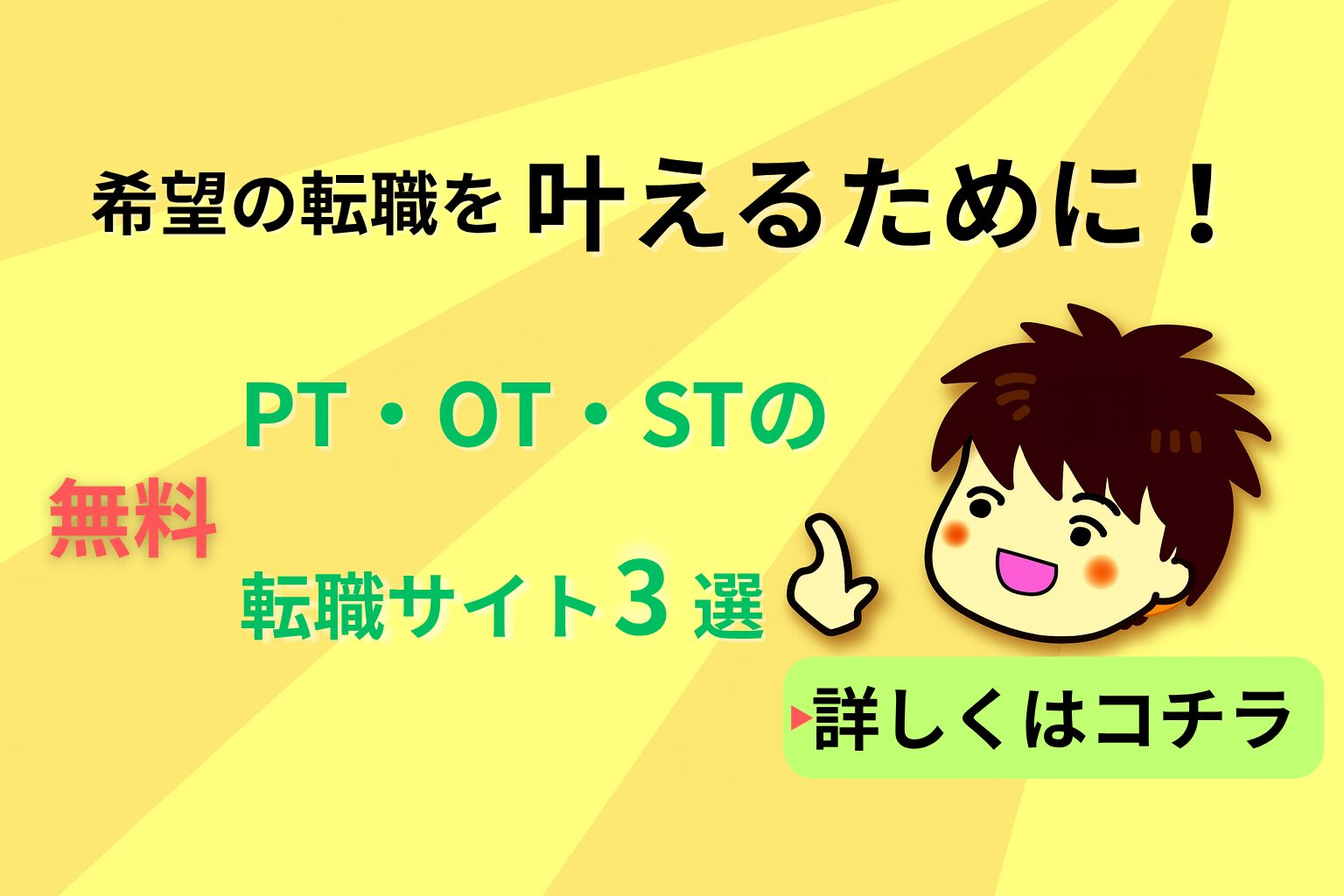運動学習において効果的なフィードバックの頻度とタイミング

あなたは、フィードバックの本当の意味をご存知でしょうか?
フィードバックとは、他人が指摘することを意味すると思っている人はいませんか?
もし、フィードバックの本当の意味を知らなかった人は、是非読んでみてください。
フィードバックを理解していれば、患者さんの運動学習だけでなく、後輩指導などにも活用できます。
今回は、フィードバックとは何か、フィードバックを与える頻度とタイミングについても解説します。
運動学習を勉強していて、いろんな用語が出てくるかと思いますが、それらをわかりやすく説明しながら解説していきます。
スポンサーリンク
目次
フィードバックとは
冒頭でも書いていますが、フィードバックは他人が指摘することを意味する言葉ではありません。
フィードバックの本当の意味は、目標値と得られた結果を埋めていくにあたって阻害している原因(情報)を操作することをいいます。
難しいので簡単にいうと、フィードバックとは原因(情報)を探し、修正することをいいます。
そして、得られた原因(情報)を元に、目標値と得られた結果を埋めていく過程を学習というのです。
フィードバックには、外的フィードバックと内的フィードバックがあります。
・自己以外から検出された情報を元に、修正していくことを外的フィードバック
・学習者自身が検出した情報を元に、修正していくことを内的フィードバック
といいます。
外的フィードバックとは
例えば、鏡を見ながら(視覚情報)「もっと足を上げてください」(聴覚情報)のように、他人から指摘を受けるなどは、外的フィードバックにあたります。
運動学習を学ぶにあたって、結果の知識(KR:knowledge of results)やパフォーマンスの知識(KP:knowledge of performance)という用語もありますので説明しておきます。
結果の知識とは得られた運動の結果(情報)をいい、パフォーマンスの知識とは目標としている動作の情報をいいます。
つまり、運動学習の最終地点は、結果の知識とパフォーマンスの知識の差がなくなった状態であるといえます。
結果の知識やパフォーマンスの知識は、自己以外から得られる情報であり、これらの情報提供は運動を学ぶ初期段階に活用されることが多いです。
内的フィードバックとは
例えば、立ち上がり運動をする際に、鏡を見て(視覚)、四肢の位置が正確であったか(体性感覚)を知覚し、「股関節と膝の動きがバラバラだなぁ~」など自己内部で検出するのは、内的フィードバックにあたります。
内的フィードバックは、運動学習の中盤~終盤にかけて活用されることが多く、内的フィードバックが運動学習の過程には重要になってきます。
後述する外的フォードバックの頻度とタイミング(下の見出し)でも解説しますが、他人から「ここをもっとこうして、ああして」という指導は、逆にパフォーマンスを下げることにもなります。
注意をどこに向ければ良い?
学習の初期の段階では、自己の身体に注意を向けるよりも、自己以外の手がかりに注意を向けるほうがパフォーマンスは向上しやすいといわれています。
ちなみに以前にも、このようにな記事を書きました。
その記事では、バランスが要求される不安定な状態では、身体内部に注意を向けるよりも、身体外部に注意を向けるほうが姿勢動揺が軽減するといった内容を書いています。
これは、運動学習においても同じことで、不慣れな状態では身体外部の情報を頼りに、まずは大ざっぱに身体の使い方を覚えるほうがパフォーマンスは良くなります。
なので、指導者はまずは大ざっぱにパフォーマンスの知識を与るのです。
例えば、立ち上がりでは「このタイミングで股関節と膝を伸ばして!」と声掛けするのではなく、前方の机を持ち、「頭を机のほうに近づけてから、天井方向へ身体を起こしていきましょう。」と声掛けするほうが良いです。
このように、外部の手がかりを頼りに運動方向を誘導するほうが学習しやすいということです。
ただし、運動学習が進んできて、更に運動の精度を高めていこうと思えば、次は自己内部に注意を向けていくことが大切です。
固有感覚を用いて、各関節がどのように動いているのかに注目してもらうのです。
運動学習の最終ゴールは自動化です。つまり、無意識な運動が可能になるということです。
運動を無意識まで落とし込んでいくと、また身体外部に注意を向ける余裕すら生まれてきます。
フィードフォワード制御とは
運動の無意識化・自動化が可能になれば、フィードフォワード制御も可能になります。
フィードフォワード制御とは、フィードバック情報がうまく使えないような素早い運動の際にみられます。
あらかじめ目的に必要な運動を脳内で予測し、出力を調整することをいいます。
実は、日常生活の手慣れた運動は、ほとんどがフィードフォワード制御です。
フィードフォワード制御は大脳を介さない中枢性の制御であり、これをオープン・ループ制御(開ループ)いいます。
一方、フィードバック制御は視覚・聴覚・体性感覚などを一旦大脳を介して判断するため、反応に遅れが生じてしまいます。フィードバック制御は、クローズド・ループ(閉ループ)といわれています。
スポンサーリンク
外的フィードバックの頻度とタイミング
Salmoni et al(1984)によって提唱されたガイダンス仮設によると、頻繁な外的フィードバックは学習者がそれに依存してしまい、逆にパフォーマンスを下げるといわれています。
外的フィードバックを与える目的は、まずは正しい運動(パフォーマンスの知識)を大ざっぱに学習することです。
これは学習初期には効果的ですが、内的フィードバックを促進するには学習者自身が得られた運動の結果を自己解釈する時間が必要です。
学習初期においても、毎回の外的フィードバックを与えるよりも2回に1回のほうが以後のパフォーマンスは良いという研究報告もあります。
そして、より良い運動パフォーマンスを目指すには、フィードバックの回数を減らす漸減的フィードバックを意識するべきです。
また、運動の結果の後すぐにフィードバックを与えるよりも、少し間を置いてから(8秒以上)フィードバックするほうが、その後のパフォーマンスは向上するといわれています。
学習者自らが、アクティブに考える時間が多くなると学習効果は高まります。
イメージ・トレーニングは有効か?
頭の中で、運動イメージを繰り返し行うことをメンタル・プラクティス(MP:mental practice)といい、スポーツの世界でよく用いられています。MPを行うことで、科学的にも脳の活動を認めています。
イメージ・トレーニングでいうと、他人がしているのを観察するだけでも、パフォーマンスは向上するといわれています。
運動の上手い人を観察するとパフォーマンスの向上には良いとされていますが、逆に下手な運動を観察してもパフォーマンスは上がることもあります。
下手な運動を観察すると、学習者自らでどこが間違いでどのようにしてそれが起こっているのかを考えるきっかけにもなるからです。
合わせて読んでおきたい記事