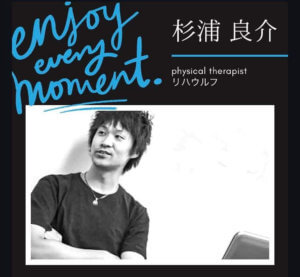どうも、かずぼーです。
今回は、2020年8月15日「訪問リハビリ」の本を出版することになった”リハコネ代表の杉浦さん”に本書完成までの裏側をインタビューしてみました。
- 出版に至った経緯
- いつ頃から本を書きはじめた?
- 出版のどんなところが大変だった?
- 他の訪問リハの本と違うところは?
などなど。
さらに、どんな思いで本にしたとか、出版までのゴタゴタ、工夫したこと、執筆の段階でどんな話が出てたのかなど熱い裏話が聞けました。
やっぱ杉浦さんは面白いですね!
是非、最後まで読んでみてください。
杉浦さんのTwitter▼
新着ランキングは
ずっと1位をキープ!#感謝本が売れる=訪問リハが広まる
コツコツ広めます😺
みんなで
訪問リハを広めよう〜!#リハコネ https://t.co/URrX06JZeO pic.twitter.com/oozAS0jbgp— 杉浦良介🐺8/15に訪問リハの本出る📙 (@RihaWolfnet) August 12, 2020
スポンサーリンク
目次
杉浦さんの自己紹介
- 理学療法士11年目。訪問リハ9年経験(訪問看護3年、訪問リハビリ6年)
- 訪問リハコミュニティ「リハビリコネクト」代表
- 得意なことは訪問リハ全般
【2017年】
訪問リハブログ「リハウルフ」で2年間で300記事以上
【2018年】
書籍寄稿「コミュニケーションを止めるな!」
【2019年】
- 訪問リハセミナー2019年6回講師(受講者述べ250名以上)を務める(詳細)
- 株式会社gene様「リハノメラーニング出演」(詳細)
- 株式会社クーリエ様「みんなの介護」ライター(過去の執筆) 2019年3月〜
- 株式会社ビジケア様「訪問看護経営マガジン」編集部長 2019年10月〜
【2020年】
- 8月15日:書籍出版「リハコネ式! 訪問リハのためのルールブック」
なにがきっかけで本を出すことになったんですか?
なんで本を出すことになったんですか?
きっかけは?
訪問リハビリの本を出したいなって思ってて、
最初は自費で出版しようとしてたんです。
それで、Twitterで、
「訪問リハの本を書いている」「サインしたいから本書いてるんだー」
って何度もtweetしてたら、geneの張本さんに「うちで書く?」って言われて、それがきっかけですね。
なんで訪問リハの本を出したかったんですか?
訪問リハを広めたいって考えてて。
具体的に誰に広めたいんですか?
全国にです。
訪問リハって、介護保険域の1%も満たないくらいですよ。
それくらい訪問リハって、全然使われていないです。
訪問リハやってるセラピストが少ないし、まだまだ広められると思ってるんです。
「リハコネ式! 訪問リハのためのルールブック」は9職種、22人が書いた本
今回、9職種22人で書いたんですけど、全員が今訪問に関わる仕事をしている人たちなんですよ。そこにこだわりました。
訪問リハの現場の人たちが書いた本って、あまりないんです。
訪問リハを全然やったことない人が書いてたり、監修になってたり、大学の教授とか、どこかの協会が出してたりするのが僕はちょっと気にくわなくて(笑)。
そうじゃなくて、今働いてる人のリアルを伝えたかったんです。
今回、出版した本で"監修をおくかおかないか"も考えたんですけど、あえて訪問セラピストである自分が監修になりました。
有名な医者を監修にすると本の価値はあがるように思うかもしれませんが、現場のリアルを伝えたかったので。
杉浦さん、なんかふざけてる人だと思ったら訪問リハビリ詳しいんですね!(笑)
めっちゃ詳しいですよ、正直。(笑)
誰にも負けないですか?
負けないですね!
見た目以上に真面目なんですね。(笑)
11年の理学療法士歴で9年やってますからね。
スポンサーリンク
他の訪問リハの本とのの違いは?
他にも訪問リハの本っていっぱいあるじゃないですか?
この本は、他と何が違うんですか?
多職種連携の本って、結構あるんですよね。
多職種だと、医者とか、看護師とか、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士って分かれるじゃないですか。
今回出した本は、多サービスに注目して、
訪問診療、福祉用具、訪問看護、訪問介護とか、職種ではなくて"サービスからみた訪問リハで大事なメッセージ"を伝えています。
サービス事に書いてる本ってないと思うんです。
なるほど。
より利用者さん目線ってことですね。
在宅で訪問リハを受ける利用者さんって、いろんなサービスを受けるじゃないですか?
訪問リハをやりながらデイサービスに通ったり。
利用者さんを主体に考えたときに、この利用者さんに必要なのは訪問看護かもしれないし、訪問診療かもしれないし、通所リハビリかもしれないしって考えるんです。
だから、いろんなサービスを知っておかないといけないし、役割とか制度のことも知っておかないといけないですよね。
なので、9職種が訪問セラピストに向けて「こんなサービスがありますよ。役割はこんなんで、知っておく制度はこんなのがありますよ」ってことを伝えています。それが第3章で書かれています。
第2章では、訪問セラピストに一番必要な制度のことが書いてます。
- 訪問リハの制度
- 訪問看護の制度
- 介護保険の制度
- 医療保険の制度
- 障害の制度
- 公費の制度
これらを訪問セラピストの視点で書いてます。
他の本だと、制度のこと書いていても使えないことがあるんですよね。
この本はA5サイズのコンパクトな本なんですけど、大事なところをギュッとまとめた本になってます。だから読みやすいですよ。
この本は、訪問リハビリに必要なことしか書いてないってことですよね。
そうそう。
ほんとにそうです。現場で使えるもの。
訪問リハ以外の病院のセラピストにも読んでほしいですね。
回復期だと在宅に退院させるじゃないですか。
で、在宅の制度を知らないセラピストも多いと思うんです。
病院から在宅に帰る患者さんはどんなサービスが使えるのかも知っておかないといけないと思うんです。
この本で、一つ一つの制度とサービスが全部網羅して書いているので、だから勉強になると思いますよ。
いつから書き出したんですか?
いつから書き始めたんですか?
書き始めたのは昨年の11月からです。でも本を書くのが決まったのは7月くらいです。
打ち合わせはあったんですか?
名古屋にも行きましたし、社長(株式会社geneの張本さん)にも会いましたよ。社長頭痛だったので、そのとき。
社長はどんな人ですか?
良い人ですよ。奢ってくれました(笑)。
出版の大変だったところは?
出版でどんなどころが大変でした?
僕が編集、監修という立場でやっているので、一つの本を仕上げるのに「ここの部分はこう書いてほしい」とかってあるじゃないですか。
でも、9職種22人みんな書きたいことがバラバラなんですよね。多職種の思いがあるので。
9職種22人の思いをまとめて一つの本に仕上げるってところが大変でしたね。
今回のこの本自体が多職種連携みたいな感じでしたね。
例えばどんなやり取りがあったんですか?
それはあまり言えないです。
ちょっとバトルっぽいところもあったので。(笑)
いいですよ、言ってもらって。(笑)
じゃあ、言える範囲で。
例えば、訪問セラピストとして「理学療法士としては、こういうことを追加して書いてほしい」ってお願いしても、
「自分の職種としてはこれが大事だと思っている」みたいな意見のすれ違いがあって。
多職種の意見を尊重したいなと思って、結局自分が折れたってことが多かったです。(笑)
訪問リハビリを全国に広めたいのはなぜ?
「訪問リハを広めたい」っていうのが大きな目標があって。
訪問リハを始める人を増やさないといけないし、そのためには訪問リハをする人が楽しくやり続ける必要もあると考えています。
訪問リハが周知されていないので、多職種やまだやったことがない人、地域にも訪問リハってこういうものっていうのを知ってほしいです。
訪問リハビリを広めたいのはなんでですか?
「訪問リハビリの数が少ないから広めたい」っていうのがあるかもしれないですけど、訪問リハを増やしていくことって必要なんですか?
地域格差みたいなところもあるんですか?
ありますよ。
東京と大阪がダントツで多いです。
全国で1万千くらい事業所がある中で、東京と大阪だけで2割くらいありますから。
僕は静岡県の磐田市に訪問リハビリを広めたんですよ。
なかったんですか?
全然認知されてなかったので、周知させたんですね。
自分が地域にどんどん出たことで、セラピストも地域に貢献できるなっていうのを経験して、
自分が訪問リハをやることによって、利用者さんの生活がどんどん良くなったし、地域が豊かになってるなって。
自分の地域で身をもって経験できたので、その経験を各地域でも広まれば、地域がもっと豊かになっていくのかなって思いを込めて、訪問リハを広めたいなって考えています。
訪問セラピストは全国各地をもっと豊かにできると信じているので。
放っておくと悪くなるけど、自分が関わることで利用者さんが良くなるってことがわかるんです。
関わる前からどうなるかわかるものですか?
面談して、話するだけでわかりますよ。
うちは回転率が高い事業所なので、新規だけで年間70人くらいみてるので、面談のときにこの人どうなるかってだいたいわかりますよ。
住宅改修、福祉用具を入れただけで、それがきっかけで良くなることもあります。
訪問セラピストから見た病院セラピストの印象
回復期も見てるんでしたっけ?
見てますよ。
全職員兼務してます。
回復期どうですか?
どうですか?(笑)
思うことないですか?
思うこといっぱいありますよ。(笑)
回復期のことは、未だによくわからないですけど、最近思うのは退院直前は「退院準備期」みたいにしたほうがいいかなって思っていて。
退院直前になって、「最後まで見守りするな」「最後まで口頭指示をするな」「最後まで介助するな」って思うんです。
もちろん、リハビリ介入中は難しいですよ。
でも在宅に帰るとセラピストが関わらない時間が圧倒的に多くなるのですから、退院の直前までセラピストの見守りとか介助とか指示がないと動けないようではダメだと思うんです。
なるほど。
僕も回復期は8年くらい勤めていましたが、それは難しい問題ですね。(笑)
というのも、自立してる患者なら問題ないですが、絶対介助が必要な患者もいるじゃないですか。
そういった患者には、家族に来てもらったり、セラピストによっては写真を取って介助方法を指導したりする人もいます。
そこまでしていても、自宅に帰ると環境が変わったり、能力が変わったりするじゃないですか。
やっぱり病院でできるリハビリには限界ってあると思うんですよね。
僕たち訪問セラピストは、直接家族に指導できますよね。
回復期って家族に指導する機会って少ししかないじゃないですか。
だから、退院した後は訪問リハに任せてほしいですね。
本の中では、「回復期ってこういうところで、訪問リハビリに求めることはこんなこと」っていうのは、回復期に勤める喜多さんが書いてくれてるんです。
急性期が訪問リハビリに求めることは、えるさんが書いてくれています。
杉浦さん、ありがとうございました。
「リハコネ式! 訪問リハのためのルールブック」興味のある人は、是非手にとってみてください。
ここから下は、おまけです。(笑)
外来リハって、ハミってますよね?(笑)
僕が外来なんですけど、外来リハってハミってません?(笑)
外来はどういう位置づけで考えてます?
外来って、難しいですね。
やっぱり外来ってハミってますよね?(笑)
ハミってますよ。(笑)
外来は、今回の本で入れてないですもん。
外来ってなんなんですか?(笑)
ハミってますね。
そうなんですよ。
ハミってるんですよ。
外来って、何期になるんですか?
一応、急性期になるんですか?
ん~、維持期に近いかも。
僕の中で、外来リハビリが本当に必要な人って1割くらいだと思ってるんですよ。
だって、ぎっくり腰とかって外来に来ても勝手に治るじゃないですか。
膝痛めたって言って来ても、安静にしてれば治るじゃないですか。
肩上がらないって言って来ても、安静にして炎症ひくの待って、その後動かせば治るじゃないですか。
そんな人は、正直自分でどうにかできるんですよ。実際には外来リハ必要な人は多いんですけど、ぶっちゃけ勉強すれば自分で治せるんですよ。
でもやっぱり外来リハ必要な人もいるんですよ。
外来がなかったら、本当は訪問リハ受ける人が自分で動いて来れるから外来リハビリに来るんですよ。
訪問リハって、そもそも通院困難な人にやるものなので、通院が可能な人は外来いきますよね。
介護保険を持たない高齢者が外来にいくんじゃないですか。
あとは、それ以外の医療保険の人たちがいくんですよね。
だからハミってるんですよ。
介護保険をもっている以上は、介護保険領域でリハしますよね。
国の流れで、介護保険持ってる人は介護保険でってなってますもんね。
外来リハは介護度増悪を予防している?
視点を変えると、外来リハで介護度増悪を止めてるともいえますね。
予防ですね。
たしかに、介護保険にいく前の高齢者を見てるんですもんね。
そうそう。
だってね、この人介護保険にいってもいいんじゃないかっていう人でも、介護保険使わずに踏ん張ってる人いますよ。
一時的に痛みとかで動きが悪くなって、それで外来に来て、治ってそのまま生活に戻る人も多いですからね。
外来がなかったら、痛みが治らずグダグダになって、能力落ちちゃいますよ。
僕のクリニックはリウマチ専門なんですけど、生物学的製剤が出だしてから、かなりリウマチの症状を押さえられる人が増えたんですよね。
少し前だったらバンバン炎症出て、廃用が進んで動けなくなるような人でも、動けるようになって。変形は残ったままですけど。
そういう人は、介護保険と医療保険の間を迷ってるなって感じです。
外来がなかったら介護保険に流れてますよね。
そうですよね。
介護にならないように、最初に支えているのは外来ですもんね。
予防になってるってことですよね。
介護保険で"要支援"が予防って言われてますけど、その前で支えているのは外来かもしれないですね。
マジでそうだと思います。
介護保険取るか取らないかきわどい人多いですよ。
たしかにそうだ。
それ、今度記事に書こう。
>>要支援のリハが予防だと思っていたけど、1番の予防は外来リハかもしれない!