欲しい本が必ず見つかる!目的別「理学療法士のおすすめ参考書52選」をご紹介

療法士(PT・OT・ST)は、専門職として臨床で悩むことって多いですよね。
あなたは日々どのように自己研鑽をしているでしょうか?
僕がおすすめしたいのは、参考書をひたすら読むことです。
もちろん、セミナーに参加したり、職場の先輩に教えてもらったりして知識を補充していく場合もありますが、セミナーってわざわざ会場に足を運ばなければいけませし、職場に頼れる先輩がいるとも限りませんよね。
参考書をひたすら読むことのメリットは、家でゴロゴロしながら、時にカフェでコーヒーを飲みながらでも勉強できてしまう点です。読書は、時間も場所も縛られないのでコスパは抜群に高いです。
勉強熱心なら「参考書を読んで勉強しよう」と思い立ち、本屋に足を運ぶことってあると思うのです。
「触診の勉強がしたいな~」
「でも、どの参考書が良いのかわからない・・・」
たくさん並ぶ書籍の前で、何十分もページをパラパラめくり立ち読みしながら悩むのはあるあるですよね。
僕は9年の理学療法士歴で、新人の頃から勉強のためにとリハビリ関係の参考書を買い漁っていました。
そんな読書好きの僕が、理学療法士におすすめの書籍をご紹介します。その数52冊!
本屋へ行く手間を省き、全てここで網羅できれば完璧です!
ただランダムに紹介してもわかりにくいので、学びたい書籍が見つかりやすいように「目的別」にご紹介します。
紹介する参考書カテゴリーは、
- 解剖学・生理学
- 触診
- 理学療法評価
- 疾患別リハビリ
- 治療方法
- コミュニケーション
です。
専門書は一冊3,000〜20,000円くらいとピンキリ。
いずれにしても一般書に比べれば高額なので、買うなら絶対に外したくないですよね。
選んだポイントは、「わかりやすい書籍か!?」この一点です。
僕の独断ではありますが、読んでみると絶対臨床で役立つ本しか紹介していません。
スポンサーリンク
目次
おすすめ参考書:「解剖学・生理学」編
解剖学や生理学など、人体を診る上で基本的な知識が学べる書籍をご紹介します。
1.カパンジー(上肢・下肢・体幹)
解剖学や運動学を模式的に理解するなら、カパンジーは欠かせません。
こちらのシリーズは、上肢・下肢・体幹の3つがあります。
カパンジー機能解剖学 I (1) 上肢
カパンジー機能解剖学 II (2) 下肢
カパンジー機能解剖学 III (3) 脊椎・体幹・頭部
2.ベアー コノーズ パラディーソ 神経科学―脳の探求
カラー版 ベアー コノーズ パラディーソ 神経科学―脳の探求
脳は世間的にも、まだまだわからないことの多い臓器です。これからの研究で明かされる事実もきっと多いでしょう。
現時点でわかっていることを、研究結果をもとに理論的に解説されています。脳卒中患者に関わることの多い療法士、特に高次脳障害に関することはこちらの書籍で学ぶと新たな発見があるでしょう。
3.脳卒中ビジュアルテキスト
脳の主要血管や血管の支配領域を理解するならこの一冊。めちゃくちゃわかりやすいです。脳卒中患者を担当するなら、絶対読んでおくべきです。
4.CD-ROMでレッスン 脳画像の読み方
療法士も脳画像を診ることがあると思います。脳画像を診る目的は、脳画像から考えられる機能障害の把握と予後予測のためです。
脳卒中患者を診る前には、絶対脳画像は診ておくべきです。この書籍が簡潔でわかりやすいので紹介しておきます。
5.リハビリテーション基礎医学
こちらは少々古い本ですが、絶対目を通しておきたい内容ばかり。
例えば、皮膚や筋、骨はどれくらいで治癒するの?など、術後の患者に関わる療法士にとっては知っておいたほうが良いことばかりが記載されています。こういった基本的な治癒過程や治癒期間を知っているだけで、患者に「一般的にはこれくらいで治癒すると言われています」と説明できるでしょう。
急性期や回復期に勤めている療法士は、絶対持っておいたほうが良いですね。これは僕も重宝している一冊です。
6.人体の構造と機能:解剖生理学
こちらの書籍は、小難しい内容は一切なく、療法士が知っておきたい解剖・生理がわかりやすく解説されています。
僕は、こちらの書籍を国家試験前に購入しましたが、試験用に作られたのではないかと思うほど国家試験に使える書籍です。学生にもおすすめの一冊です。
7.アナトミー・トレイン [Web動画付] 第3版: 徒手運動療法のための筋筋膜経線
こちらは筋膜治療を理解する上で、基礎となるアナトミー・トレインの書籍です。有名です。
8.【解剖学アプリ】teamLabBody-3D Motion Human Anatomy
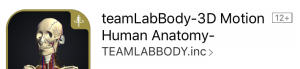
teamLabBody-3D Motion Human Anatomy- - TEAMLABBODY.inc
書籍ではありませんが、解剖学アプリもかなり使えます。
下記記事で詳しく解説していますが、人体を3Dで描写しているアプリは簡易版人体模型といえるくらい優れたものです。
一つ上の治療家を目指すなら絶対に持っておきたいアプリです。
解剖学アプリの詳しい解説はこちら▼
[st-card id=8186 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]おすすめ参考書:「触診」編
理学療法士には欠かせない触診のおすすめ本をご紹介します。
9.運動療法のための 機能解剖学的触診技術 上肢
触診の書籍で最もわかりやすいのがこちら。骨・筋・靭帯の触診をマスターするなら持っておくべきです。
10.運動療法のための 機能解剖学的触診技術 下肢・体幹
こちらは下肢・体幹の触診についてです。こちらも同じくわかりすい。
11.動画でマスター! 機能解剖学的触診技術 上肢
こちらは書籍内にQRコードが載せてあるので、どこでも動画で触診技術が学べます。
12.動画でマスター! 機能解剖学的触診技術 下肢・体幹
こちらは、下肢・体幹の触診技術が動画で学べます。
おすすめ参考書:「理学療法評価」編
理学療法士が行う基本的な評価内容が記載されているおすすめ本をご紹介します。
13.ビジュアルレクチャー理学療法基礎評価学
まずは、こちらの書籍で評価内容を網羅的に学習しましょう。
14.ベッドサイドの神経の診かた
理学療法士が関わる患者は、大きく中枢神経疾患と整形外科疾患に分けられます。
こちらは、脳卒中や脊髄疾患など中枢神経疾患の方への評価項目が丁寧に解説されています。かなり基本的な内容ですが、理学療法士なら絶対に持っておきたい一冊です。
15.リハビリテーション リスク管理ハンドブック
リスク管理は、運動療法を行う上で欠かせません。高齢者に多い心疾患や呼吸器疾患を呈する患者を担当するなら、予習・復習として使える一冊です。
16.筋緊張に挑む―筋緊張を深く理解し、治療技術をアップする!
筋緊張を深堀した内容です。筋緊張の異常は脳卒中後遺症の方だけでなく、運動器疾患でもみられる過緊張も含まれます。
筋緊張を正しく理解すれば、筋緊張に対してどう治療を展開していけば良いのかが見えてきます。
17.感覚入力で挑む―感覚・運動機能回復のための理学療法アプローチ
こちらも感覚障害を深く理解するのに欠かせない一冊です。
感覚とは何なのか、どうアプローチをしていけば良いのかがわかる書籍です。
18.前庭リハビリテーション めまい・平衡障害に対するアプローチ
前庭機能へアプローチする理学療法士は少ないと思いますが、前庭系はバランス能力に欠かせない重要な機能です。
ただ闇雲にバランス練習をしてしまいがちな療法士は、この本を読んでみてください。どのような目的でバランス評価や練習をするのかが理解できるようになると思います。
19.動作分析 臨床活用講座―バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践
基本動作練習を提供する理学療法士は、全体持っておきたい書籍です。
寝返りや起き上がり、起立、歩行の評価ポイントがわかりやすく解説しています。臨床で役立つ一冊です。
おすすめ参考書:「疾患別リハビリ」編
疾患に対する理学療法アプローチについて、参考になる書籍をご紹介します。
20.関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 上肢・体幹
「触診」編でもご紹介しました運動療法のための 機能解剖学的触診技術 上肢と合わせて持っておきたい書籍です。
整形外科疾患に対するアプローチ方法が具体的に紹介しています。
21.関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション
こちらも同じく運動療法のための 機能解剖学的触診技術 下肢・体幹と合わせて持っておいたい一冊。
22.ここがポイント!脳卒中の理学療法
脳卒中の基本的な内容から評価、治療に関して写真付きで分かりやすい解説されている書籍です。
脳卒中の理学療法を学ぶならこの一冊です。急性期から回復期、維持期に関わるどの療法士にもおすすめです。
23.脳卒中理学療法の理論と技術
脳卒中といっても、軽度から重度までその症状は様々です。運動療法の知識だけでは、脳卒中のリハビリテーションを理解することは難しく、画像所見から考えられる予後予測や装具療法の治療理論なども学ぶ必要があります。
脳卒中の知識をより幅広く学びたい人におすすめです。
24.姿勢から介入する摂食嚥下 脳卒中患者のリハビリテーション
実は体幹・頚部の機能と摂食・嚥下機能は密接に関係しています。
理学療法士や作業療法士は、直接摂食・嚥下機能へアプローチすることはありません。この書籍を読んでみると姿勢からも摂食・嚥下機能へアプローチできることがわかります。
25.リハビリスタッフ・支援者のためのやさしくわかる高次脳機能障害
理学療法士や作業療法士は、言語聴覚士よりも高次脳機能障害の知識が不足しがちです。
日常生活場面で高次脳機能障害が顕著に表れている患者に対するリハビリを提供するなら知っておきたい知識ですよね。
いざ、高次脳機能障害を勉強しようと思っても難しく感じることもあると思います。
まずは、わかりやすく書籍を読んでみて大枠を掴むことが大切です。そんなわかりやすい書籍がこちらになります。
26.高次脳機能障害学
高次脳機能障害をより深く学びたい人におすすめです。研究結果なども多く記載されており、理論的に解説されています。
27.図説パーキンソン病の理解とリハビリテーション
パーキンソン病についてはこちらがおすすめです。
いわゆる4大症状といわれる、安静時振戦、固縮、無動、姿勢反射障害などのメカニズムがわかりやすく解説されています。
28.パーキンソン病の理学療法
こちらはパーキンソン病の基本的な内容から、評価項目や治療方法などが解説されています。
より詳しく理解したい人におすすめです。
29.循環器理学療法の理論と技術
心疾患や呼吸器疾患などの循環器をすることは、リスク管理をする上でも重要な知識です。
とても読みやすく理解しやすいのでおすすめです。
30.関節リウマチ (リハ実践テクニック)
関節リウマチは生物学的製剤などが処方されるようになり、痛みに苦しむリウマチ患者が劇的に減少しているといわれています。
理学療法士として、リウマチ患者に関わるときには愛護的なROM訓練や筋力増強運動、それ以外に患者の生活に合わせた装具の処方、日常生活動作の指導なども重要になってきます。
こちらは、リウマチ患者を診るには持っておきたい書籍です。
31.肩関節拘縮の評価と運動療法
肩関節の拘縮は療法士が難渋する症状の一つです。
整形外科クリニックに勤めている僕も、肩関節の症状に悩む患者をよく診ることがあるので何度も読み返しています。
32.図解入門 よくわかる腰痛症の原因と治し方
リハトラという、療法士界では有名なブログの運営者が出した書籍です。
一般の方でもわかりやすい内容ですが、専門家でもかなり勉強になる内容です。腰痛を理解するなら持っておいて必ず持っておくべき一冊です。
33.英国医師会腰痛・頚部痛ガイド―解剖、診断、治療、そして生活指導と運動療法の詳細
こちらは腰痛・頚部痛に関する書籍で、かなりまとまっている内容で理解がしやすい書籍です。
34.極める変形性股関節症の理学療法―病期別評価とそのアプローチ (臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス)
変形性股関節症の基本的な概要と評価方法が中心に解説されています。
35.股関節理学療法マネジメント−機能障害の原因を探るための臨床思考を紐解く
股関節の解剖と評価、治療が写真付きで解説されています。
股関節に特化した内容で、臨床で役立つ書籍です。
36.極める変形性膝関節症の理学療法―保存的および術後理学療法の評価とそのアプローチ (臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス)
整形外科クリニックでも症状の多い膝関節痛。その多くが変形性膝関節症です。
膝関節の症状をどう評価し、治療を展開するのかわかりすく解説されています。
37.膝関節理学療法マネジメント−機能障害の原因を探るための臨床思考を紐解く
膝関節に特化した内容です。
こちらも膝関節の解剖学から評価方法が写真付きでわかりやすく解説されています。
38.臨床実践 足部・足関節の理学療法 (教科書にはない敏腕PTのテクニック)
足部の理学療法ならこちらがおすすめです。足関節の解剖から評価の方法、テーピングの仕方など治療内容が幅広く紹介されています。
39.痛み学 -臨床のためのテキスト-
痛みの書籍は沢山ありますが、どれが良いかわからない人はこの書籍で間違いないです。
痛みに関して幅広く学ぶならこの一冊がおすすめ。
40.ペインリハビリテーション
痛みは理学療法士が遭遇することの多い症状です。通常、組織が傷ついたときの危険信号として痛みを発するのですが、慢性痛などは原因がないにも関わらず痛みを訴えることもあります。その内容が研究から解説されているので、読んでみると新しい発見があるはずです。
41.運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略
痛みの部位別に原因と評価方法が解説されているので、とてもわかりやすいです。
おすすめ参考書:「治療」編
理学療法士が治療技術を高めるための書籍をご紹介します。
42.理学療法プログラムデザイン〈2〉ケース別アプローチのポイントと実際
理学療法場面でよくみられる症状(例えば、膝折れなど)をピックアップして、どのようなアプローチ方法があるのかを解説しています。
43.[Ⅰ]体幹 -座位,起立,立位のリハビリテーション- (片麻痺を治療する)
体幹機能に特化した書籍です。体幹を支配する神経や反射機序などが記載されています。
研究結果を多く取り入れた内容で、治療を行うヒントになる内容ばかり。おすすめです。
44.ストレッチングセラピー
こちらは、シンプルの筋へのストレッチの内容が写真付きで解説しています。とてもわかりやすいです。
ストレッチは万能主義ですので、できるに越したことはありません。
45.人体の張力ネットワーク 膜・筋膜―最新知見と治療アプローチ
筋膜アプローチをするならこちらがおすすめです。内容はかなり濃いです。
アナトミー・トレイン と合わせて持っておくと良いですね。
46.ファッシャル・リリース・テクニック―身体構造のバランスを整える筋膜リリース技術
ファッシャル・リリース・テクニック―身体構造のバランスを整える筋膜リリース技術
筋膜治療をわかりやすく解説しているのがこちら。写真も綺麗で筋膜治療初学者向けといった内容です。
47.手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖
手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖 (GAIA BOOKS)
トリガーポイントについて学ぼうとしていた僕が、わかりやすい書籍を探して購入したのがこちら。
48.上肢の理学療法-局所機能と全身運動を結びつけるインタラクティブ・アプローチ
整形外科疾患や脳卒中など、疾患から考えられる評価方法や治療が網羅されています。
49.理学療法士のための足と靴のみかた
日本人なら、屋外を歩くときは必ず靴を履きますよね。足部がどんなアライメントをしているかも重要なのですが、その足部を覆う靴がどんな形状なのかを知ることもかなり重要なのです。靴を変えるだけで歩きやすくなる患者はたくさんいます。
理学療法士として、足部を診るなら靴も診れるともう一つ優れた専門家になれるでしょう。
50.運動連鎖~リンクする身体 (実践mook・理学療法プラクティス)
腰痛や股関節・膝関節痛などへのアプローチするなら運動連鎖は理解しておきたい内容です。
おすすめ参考書:「コミュニケーション」編
療法士は対人援助職です。患者との関係性が崩れてしまえば、いくら治療技術が高くても患者満足度は下がってしまいます。
本物の治療家は、腕が良いだけではなく、コミュニケーション能力も高いのです。
51.PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力
リハビリ現場で遭遇しそうなシチュエーションが、会話形式で紹介しています。わかりやすいので読んでみてください。
52.療法士が変わるときに手にする本
こちらは患者だけでなく、職場の同僚とのコミュニケーションにも活用できる書籍です。
コミュニケーションに正解はないですが、人間関係構築のヒントになると思います。
療法士として、出世するなら読んでおきましょう。
まとめ
目的別に欲しい参考書が見つけやすいように紹介してみました。
もちろん、ここで紹介した以外にも参考書は沢山ありますが、ここで紹介しているのは買っておいて損はない参考書ばかりなのでハズレはないはずです。
沢山の参考書を読んでみて、そして臨床で実践してみることで本物の知識・技術になるのだと僕は思っています。






















































