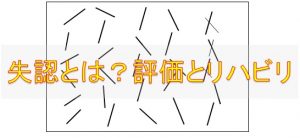リハビリ評価で使われるボトムアップとトップダウンの違いとは?評価のスピードを飛躍的に向上させる考え方
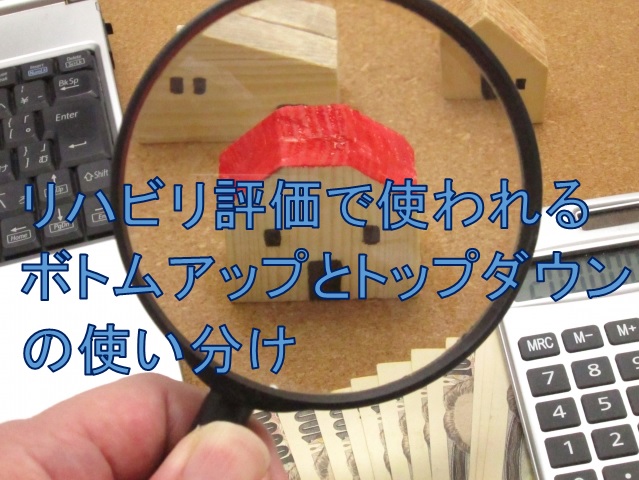
理学療法士や作業療法士が行う評価の方法として、ボトムアップとトップダウンがあります。
そもそも、これらの用語はビジネスでよく使われている用語です。
簡単にいうと、
| ボトムアップ | 部下から上司または経営者へ意見を吸い上げる |
| トップダウン | 上司または経営者から部下へ指示を出す |
このようになります。
そして、このような考え方がリハビリの評価においても用いられるようになっています。
今回は、リハビリ評価で使われるボトムアップとトップダウンの違いと評価のスピードを飛躍的に向上させる考え方をご紹介します。
スポンサーリンク
ボトムアップとトップダウンの違い
冒頭でも少し触れましたが、リハビリ評価で使われるボトムアップとトップダウンの違いをもう少し詳しく説明しておきます。
ボトムアップとは
あらゆる検査を行い、問題点をすべて出してそこから改善可能な部分を挙げていく方法のことです。
トップダウンとは
患者さんの訴えやニーズに合わせて、極力無駄のないように評価していく方法のことです。
ボトムアップとトップダウンの使い分け
臨床場面においては、ボトムアップもトップダウンも明確に分ける必要はないと言われたりもします。
確かにその通りなのですが、問題を絞っていく際に有用な使い分けがあります。
(※僕が推奨しているだけですので、あくまでも参考に!)
このあたりの使い分けができないと、評価が非常に遠回りになってしまいますので、是非知っておいてほしいと思います。
機能障害の問題点を絞っていく際には、トップダウンが有用
例えば、大腿骨の骨折で入院してきた患者さんがいたとします。
その患者さんには、まず何の検査が優先的に行われますか?
股関節のレントゲン撮影ですよね。
もしくは、疼痛検査だったりもします。
普通に考えてもらればわかると思いますが、ここでボトムアップだといって、いきなり脳画像を撮影しないですよね。
リハビリ評価も同じことで、大腿骨の骨折で入院してきているのに、最初に膝蓋腱反射をしたりしないし、する必要もないはずです。
まず、最初にやるべき評価は股関節周囲の関節可動域テストや筋力テスト、疼痛評価などです。
真っ先に、膝とか足関節の関節可動域または筋力測定をするものではないはずです。
入院している患者さんは何かしらの怪我や病気をきっかけに機能障害が起きています。
そうすると、怪我や病気の特徴、病理を知っていれば機能障害を予測し、絞り込んでいくことが可能なのです。
つまり、機能障害を評価していく際には、評価を実施する前に、どんな機能障害が出やすいのかしっかり考えてみることです!
補足:ただ、慢性腰痛などでは生活習慣も関係してくるので、このあたりはボトムアップ的に一つひとつ痛みと生活の因果関係を確認していくのが良いでしょう。
能力低下、社会参加の問題点を絞っていく際には、ボトムアップが有用
例えば、注意の同時課題が困難、さらに遂行機能障害を呈していると検査から判断できたとします。
ここで、「この人はもし動物園に行ったとしたら、道に迷ってしまうだろな~」と予測をしたとしても、
そもそも動物園に行くことがなかったら、注意も遂行機能も必要ないですよね。
「この人は左下肢の踏ん張りが悪いから、トイレに行っても立ってられないだろな」と予測することもできますが、本当に立ってられないかはわからないです。
意外と反対足一本で立ってられるかもしれません。
実習生や若手理学・作業療法士の場合、能力低下や社会参加までもトップダウンの考え方を採用してしまうために、先輩から「トイレ動作は確認したの?」なんて突っ込みが飛んでくるのです。
要するに、
能力低下や社会参加を評価していく際には、予測を立てるよりも確認してみることです!
スポンサーリンク
理学・作業療法士の経験年数が増えるとどうなるか
僕自身7年くらい理学療法士をやっていますが、新人の頃と比べて何が変わったかというと、患者さんの動作能力の底上げができるようになったというよりも、目標に行き着くまでのスピードが早くなったな思います。
新人さんでもちゃんと評価ができていれば、患者さんの動作能力は十分に引き上げることができるんです。
ただし、評価が遅くなってしまうため、後手に回ってしまうことも多々みられます。
機能障害を絞っていく際に必要ない検査をやってしまったり、能力低下・社会参加の問題点を挙げるのにあれこれ予測を立てて確認作業が遅れてしまったり。
今回説明したように、ボトムアップとトップダウンの使い分けができるようになると、評価のスピードが飛躍的に向上します。
新人の頃には、動作能力の変化に1ヵ月かかっていたところが、半月でクリアできれば、それだけリハビリの質は高まりやすくなりますよね。
最近ますます入院期間の短縮が言われるようになってきていますので、評価のスピードが上がれば、それだけ入院期間を短縮することもできるし、入院中にできるリハビリ内容が増えてきます。
そうなれば、もっともっと患者さんの活動範囲を広げることができます。
素晴らしいことですね。
まとめ
リハビリ評価におけるボトムアップとトップダウンの使い分けについて解説しました。
最後にもう一度。
機能障害はトップダウンで、能力低下と社会参加はボトムアップで評価してみると良いです。
つまり、
機能障害 → 評価する前に考えよ!
能力低下と社会参加 → 考える前に確認せよ!
です。