障害受容の過程とは?リハビリ的な関わり方について
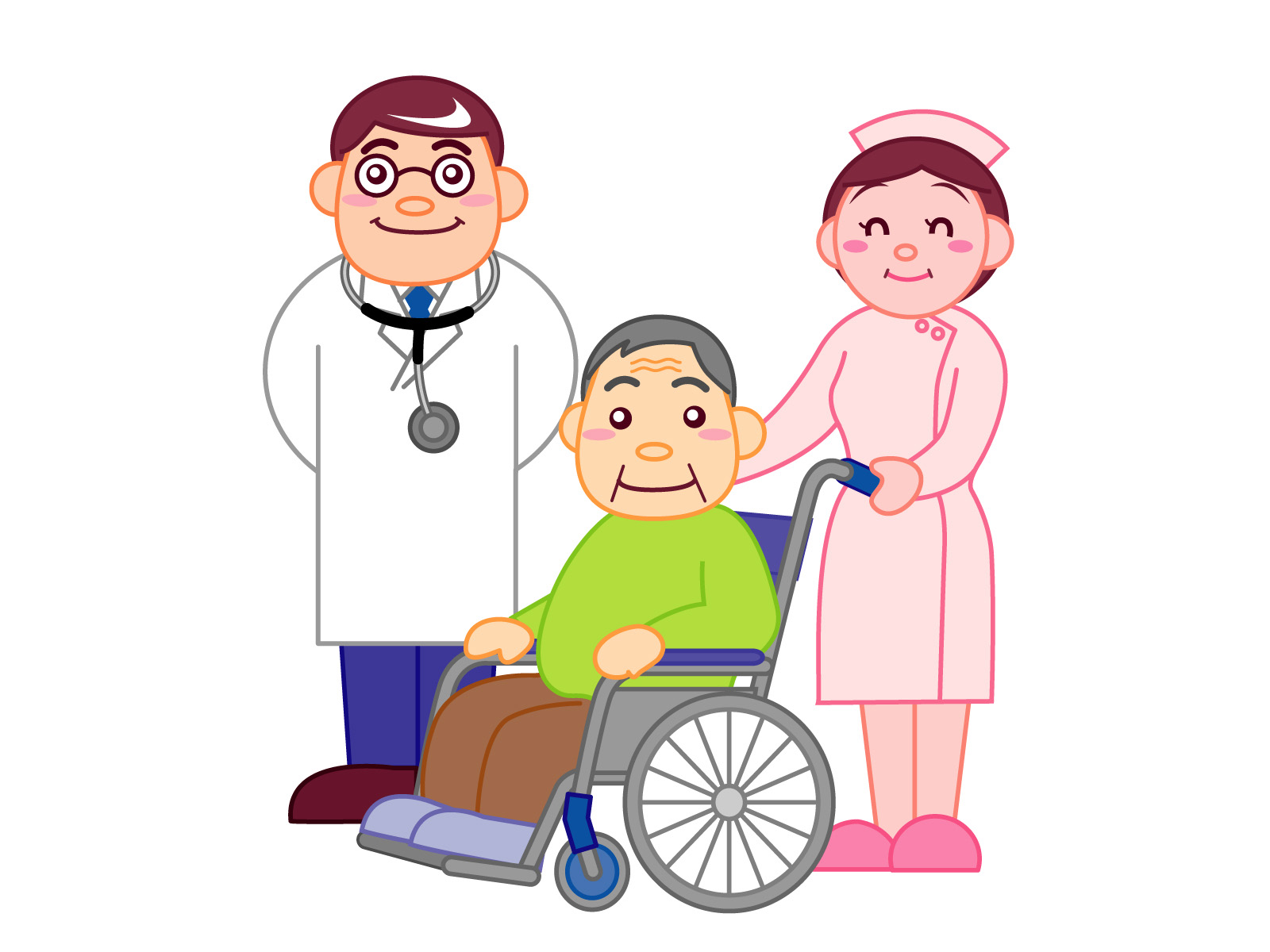
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士はどのように障害を負った患者さんと接していけば良いのでしょうか?
障害を負った人が通る心理的過程として、「障害受容の過程」というものがあります。
それは、病気や怪我の大小に関わらずほとんどの人が通る道でもあります。
障害受容とは何か?
療法士はどのように患者さんと関わっていけば良いのかを解説していきます。
スポンサーリンク
目次
障害受容の過程とは
障害受容の過程とは、コーン(Cohn)とフィンク(Fink)の段階理論がありますが、基本的には似たような解釈にはなってきます。
コーン(Cohn)段階理論は、①ショック期、②否認期、③混乱期、④解決への努力期、⑤受容期の過程を踏むことをいいます。
しかし、障害を受け入れる(受容する)だけでは不十分であり、障害を負っているけれども、毎日が安心して生活できるところまで目指すべきです。
つまり、生活に適応する⑥適応期までが障害受容の最終ゴールといえます。
①ショック期
障害を負った直後で、集中的に治療を要している時期のことをいいます。
この時期は、特に生命の危機的状況、身体的な苦痛を伴っている場合が多く、心理的には自分の身に何が起こったかすら考える余裕がない時期でもあります。
②否認期
否認とは、防御機制の一つであり、問題そのものが自分の中に存在することを認めないことをいいます。
「何かの間違いではないのか?」
「診断のミスではないのか?」
といった疑問や不信感から、障害を認めようとしない時期をいいます。
※防御機制とは、不快な感情が生じた場合に心理的に安定した状態を保つために発生する心理的作用のことをいいます。
③混乱期
障害を頭で理解してはいますが、
「誰のせいでこうなったのか?」
「何が原因だったのか?」
など、怒りや悲しみが強く表れる時期でもあります。
今までできていた生活ができなくなったことを受け入れられない状態にあります。
④解決への努力期
現実を理解し、今の置かれた状況を少しでも良い方向へ変えていこうと努力する時期のことをいいます。
「いつまでもクヨクヨ悩んでいてはいけない!」と考え、リハビリを頑張り始める時期にあたります。
⑤受容期
努力期でリハビリを頑張ったけれど、どうしても回復に頭打ちがみられる場合があります。
そうなったときに良い意味で諦めをつけ、他の手段で生活することや今までとは違ったところに生きがいを感じるようになる時期のことをいいます。
⑥適応期
障害を受け入れ、障害を追ったままでも代償手段を用いたり、別の生きがいを糧に生活ができる時期が適応期にあたります。
リハビリテーションとは「あたなはあなたに変わりはない」ことを受け入れる過程
今まで元気だったお年寄りの方でも、病気や怪我をすると、今までできていたことができなくなることがあります。
特に末期癌や脊髄損傷、下肢切断など、現代医学では治癒が難しい疾患ほど、患者さんは深く傷つき、絶望的な気持ちになります。
リハビリテーションとは「本来ある状態への回復」という意味をもつのですが、それは元通りの身体に戻るという意味ではありません。
当然ながら、死んだ人が生き返ることはありません。
同じように死んでしまった神経が元に戻ることもありません。
そうなったときに、どんな形であろうと「あなたはあなた自身」であり、どんな自分でも受け入れることを障害受容といいます。
障害を負った人が自分自身を受け入れていく、その過程もリハビリテーションに含まれています。
療法士の関わり方①「ありのままの患者さんを受け入れる」
障害受容の過程については前述しました。
療法士はどのように障害を追った患者さんと関わっていけば良いのでしょうか?
まずは、ありのままの患者さんを療法士自身が受け入れることです。
特にショック期〜否認期にある患者さんは抑うつ状態になりやすく、身体の回復のことなど考えることもできません。
変わってしまった自分に深く傷ついています。
関わり方はその時の状況に合わせて臨機応変に対応していくのが良いのですが、「リハビリしたら良くなりますよ。」「前より良くなってきていますよ。」といった発言は必ずしも良いとは言えません。
上記の声かけには、「今のあなたはまだまだですよ」といったニュアンスも含まれてしまうからです。
まずは、どんな姿であろうと「あなたはあなた」であるということを、療法士の関わり方で表現していきます。
声掛けよりも、むしろ側に居て患者さんの辛い気持ちをただただ聴くだけでも良いのです。
療法士の関わり方②「道を提示する」
混乱期になると、置かれた状況を頭では理解し始めるのですが、患者さんは何をどうしたら良いかわからないのです。
患者さんは医学の知識を持っていないことが普通ですので、「今後自分はどうなっていくのか」と不安になっています。
療法士は身体の動きを診たり、良くしていく専門家です。
素人と専門家の違いとは、患者さんの未来の姿を的確に想像できるところにあります。
どこにどの程度の障害があり、どうしていけば身体は良くなり、また回復の難しい機能はどこなのかがある程度予測できるのです。
その想像した未来の患者さんに近づいていく手助けするのが療法士の役目です。
混乱期にある患者さんには「こういった道で生活を取り戻していくことができる」ということを示していくことで患者さんは希望を持つことができるようになります。
療法士の関わり方③「共に悩みむこと」
解決への努力期にある場合に最も大切なことは、患者さん自身が後悔のないように障害と向き合うことです。
「もっと頑張ることができたのではないか?」
「もっと良い治療を受ければ治っていたのではないか?」
そういった気持ちを患者さんが持ってしまうと、後悔が残ってしまいます。
元通りの身体に戻ることができれば心理的負担も少なくて済みますが、後遺症が残ると予想される場合には、療法士も患者さんと一緒に悩む気持ちが大切です。
注意したいのは、下手に予後を断定しないことです。
「あなたはこういう機能障害が残るため、車椅子の生活になります。」
といった発言は治る可能性を否定されたと感じ、患者さんは深く傷ついてしまいます。
又は「リハビリを頑張れば、箸で食事ができるようになります。」「杖なしでも歩けるようになります。」といった言い方も必要以上の期待を持たせてしまいます。
もし、期待した通りに回復しなかった場合、患者さんは再びショックを受け、否認期〜混乱期に逆戻りしてしまう恐れもあります。
中には「私は歩けるようになるのですか?」と聞かれることもあります。
この質問の真意は、「私はリハビリに期待しても良いのですか?」といったニュアンスも含まれています。
「今の状況ではまだわかりません。歩けるように私(療法士)と一緒にリハビリを頑張っていきましょう」
と療法士は伝え、患者さんに希望を持ってもらう返答が良いです。
くれぐれも「歩けるようになります」とも「歩けるようにならないから車椅子を上手く使うようにしましょう」などと予後を断定しないことです。
もちろん、そのままの意味で「私は歩けるようになるの?」と質問している場合もありますので、その場の状況に合わせて対応していく必要はあります。
療法士の関わり方④「別の手段を提案する」
回復が頭打ちしてきたときに、再び患者さんは落ち込むことがあります。
そのときに患者さんは、今までリハビリを頑張ってきたのに報われない。という気持ちになってしまいます。
療法士は未来の患者さんの姿を予想し、先回りして別の手段を提案していきます。
例えば、歩く以外の代償的手段(車椅子など)を提案し、他の手段で目的を果たすことを一緒に探していきます。
このような関わり方を解決への努力期でしていくことで、患者さんは障害を受け入れやすくなります。
スポンサーリンク
障害受容は強要するものではない
療法士の関わり方について解説しましたが、少し戦略的にも見えてしまいますね。
まるで患者さんの障害受容を療法士が誘導するかのように・・・
ですが、間違っても障害受容を強要してはいけません。
今まで周りの人と同じようにできていたことができなくなったときに、立ち直れそうもないくらいにショックを受けるのは、人間として普通の反応なのです。
そこに「さぁリハビリを頑張りましょう。」といったところで、気持ちが追いつかないのは当然ともいえます。
療法士が先読みをしてリハビリを強要したり、代償手段を提案するのではなく、患者さんの心理を汲み取り、適切なタイミングで適切な声掛けや道を提示していく関わり方が良いです。
時には、努力期であったのに、また混乱期や否認期に戻ったりすることもあります。
その時には、頑張ることは強要せず、またしっかりと話を聴いてあげるところから始めるのが良いでしょう。
人は人と関わることで、自分の価値を見出す
他人と比べることで優越感を感じ、自分の価値を高めることもありますが、逆に劣等感を感じてしまうこともあります。
実は他人と比べても幸せにはなれないのです。
あるがままの自分自身を受け入れることが、幸せになる秘訣ではないかと思います。
人間は社会的な生き物であり、自分の価値は人と人との関わりの中で感じていくものです。
「あなたはあなたに変わりはない」
そう思えるなら、人はどんな形でも幸せになることができるのではないでしょうか。
そのことを伝えていくのも療法士の役目ではないかと僕は思います。
【理学・作業療法士は必見!】


